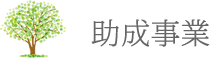助成事業は、当財団の事業の大きな柱であり、メンタルヘルスの発展に役立つ精神分析並びにその周辺領域の研究・調査に対して助成を行っております。
我が国の精神分析や臨床心理学、精神療法分野への研究助成については、近年遺伝子解析による疾病要因の研究、神経精神薬理や脳画像研究や神経心理学など生物学的な分野への研究助成に比べて大変少ないのが現状です。
我が国は世界でも例のない少子超高齢化・人口減少の時代に突入し、社会的な格差の拡大、国際的な情報化、地域における人間関係の希薄化などの社会文化的問題は背景に、覚醒剤、アルコール・ギャンブルなどの種々の依存症の増加、社会的引きこもりの増加および高齢化、児童虐待、介護ストレスの増加、自殺問題、労働環境におけるストレスの増加など数多くの「こころの問題」が増加しています。
これらの問題を考える際には生物学的なアプローチでは解明できない人間の心身における発達理論や対象関係理論、集団心理など精神分析や臨床心理学や各種精神療法関連諸分野におけるこれまでの知見や試みが大変重要となっております。
当財団はこの分野の研究者の助成を通じて精神分析学やその周辺領域の発展に少しでも寄与し、さらに、今後を担う若手の研究者の育成にも寄与したいと願っています。
この他に公共性の高い精神保健関連団体の講演会等の啓発活動や相談活動に対する助成も行っております。
1.助成の趣旨
当財団では精神分析学及びこれに関連する精神医学・人類学・心理学等の分野(以下「関連分野」という)の研究を助成、振興し、もってわが国の学術の発展と人類の福祉に貢献することを目的としています。
このために、次の事業を行います。
- 精神分析学及び関連諸分野の研究に対する助成
- 精神分析学及び関連諸分野の研究に関する学会・研究会その他に対する助成
- 精神分析学及び関連諸分野の研究に関するわが国研究者の海外派遣及び外国人研究者のわが国への招聘等の国際交流に対する助成
- 精神分析関連分野における心の健康に関する講演会等の啓発活動または相談活動
2.助成の基準
当財団設立の趣旨に則り、精神分析学の振興に寄与する貢献度によるものとし、関連分野を含めての基礎研究・応用研究・新規分野開拓等の研究のほか、研究者の海外派遣及び招聘・調査活動・精神分析関連分野における心の健康に関する講演会等の啓発活動または相談活動に対して助成を行う。
3.研究助成額
金額未定(令和7年度実績16件 総額5,420,090円)
4.応募方法及び期間
- 所定の申請用紙に必要事項を記入の上、当財団に郵送してください。
- 同一テーマによる助成申請は3回までとさせて頂きます。
- 応募期間、令和8年度助成については、令和7年12月1日より令和7年12月31日の間(必着したものに限る)
- 研究助成申請には書式1を講演会・相談活動助成申請には書式2をご提出ください。
申請書式はこちらをご覧ください
5.推薦者
- 応募には、必ず推薦者が必要です。
- 推薦者は、研究機関の役職者・学会の役員・公的機関の責任者・大学の教授等とさせて頂きます。ただし、原則本財団の役員・評議員および助成選考委員(本財団役員等という)は助成事業申請の本人または推薦者となることができません。
- 助成申込書の推薦者欄には推薦者ご署名捺印の上、ご所属・役職等を必ずご記入下さい。
- 推薦状に、推薦の事情をご記入の上添付して下さい。
6.助成申請の内以下の経費は認められませんのでご留意下さい。
- 設備(パーテーション、防音工事等の工事を伴うものなど)の設置に要する経費
- 研究機材の購入に要する経費のうち購入価格が5万円以上で当該研究終了後も他の研究等に利用できるもの (パソコン、机,椅子等の備品類)
- 学会、研究会等の管理運営に直接要する経費の補填資金と認められる経費
- 申請者個人の技能向上に資する部分が多いと考えられる派遣・学会研修参加費用やスーパービジョン費用
7.助成の決定
本財団助成選考委員会にて選考の上、令和8年4月上旬に助成の可否の決定通知をご送付致します。
尚、助成金の交付は令和8年5月末頃となります。
8.研究成果報告
助成を受けた研究等について、その成果および収支報告(要領収書(写))を助成年度終了後1ヶ月以内(4月末日まで)に提出して頂きます。
また、別途様式にて作成して頂く研究成果を当財団の年報にも掲載させて頂きます。
なお、助成期間の年度末(令和9年3月末)までに助成金に余剰が出た場合は、返還をお願いしています。
9.助成対象の研究者が次の事由に該当する場合には、助成金の交付の決定を取り消し、又は交付金の返還を求めることとしています。
- 虚偽の内容による申請を行った場合
- 選定された内容の研究を実施しない場合又は中止した場合
- 上記8の報告を行わなかった場合又は虚偽の内容の報告を行った場合
- その他本財団の助成の趣旨に著しく違背する行為があった場合
10.その他
助成対象の研究に係る知的所有権は、研究を実施した者に帰属しますが、学会・論文等で成果を発表する場合は、当財団の助成に係るものであることを明らかにするようお願いします。
また、講演会等の助成である場合は、当財団の後援であることを明記してください。
申請書式
研究及び講演会・相談活動の助成申請については、下記の様式をご提出ください。
| 助成先 | テーマ | ||
|---|---|---|---|
| 所属またはグループ名 | 代表者名 | ||
| 山梨英和大学 人間文化学部人間文化学科 |
桑本 佳代子 | 「むなしさ」に関する精神分析的研究 | |
| 福井県立大学 看護福祉学部看護学科 |
平井 宏美 | 産後の母親が養育に適応していく過程で発揮する精神的回復力(レジリエンス)に影響を及ぼす内的要因の解明 | |
| 子どものMBT研究会 | 西村 馨 | 児童や青年を対象としたMBT(MBT-C、MBT-A)の普及に向けた集中訓練の提供と臨床研究ネットワークの拡充 | |
| 相模女子大学 学芸学部 |
荻本 快 | 第二次世界大戦中の対日プロパガンダ戦略に関わった米国精神分析家たち | |
| 慶応義塾大学医学部精神神経科 家族だけ療法研究会 |
宗 未来 | 重症・遷延性の成人神経症性やせ症患者に対する家族焦点型の家族療法(”家族だけ”療法)の傾向スコア分析を用いた効果検証研究 | |
| 東京大学大学院医学系研究科 こころの発達医学分野 |
佐藤 駿一 | 被災地域一般人口における不登校コホート調査による再登校促進要因の解明 | |
| 医療法人慶神会武田病院 リワークプログラム研究チーム |
加来 明希子 | 認知行動モデルに即した効果的な復職支援の検討 | |
| PAS心理教育研究所 | 中村 有希 | 慢性適応障害の精神分析的治療要因とアルゴリズム:データベース作成と治療アルゴリズムの同定 | |
| 日本IFEEL Pictures研究会 |
長屋 佐和子 | 父親の育児参加経験による乳幼児に対する情動認知変化-日本版IFEEL Picturesを用いた検討- | |
| 保育精神分析臨床研究会 | 井上 果子 | 対応に苦慮する保育士への対応法と保育臨床支援法の検討 | |
| 日本精神分析協会 | 藤山 直樹 | こころの臨床家一般への精神分析の啓発活動のための費用 | |
| 国際力動的心理療法学会 第28回年次大会事務局 |
橋本 和典 | 福島における国際力動的心理療法学会第28回年次大会へのDr.Seth Aronsonの招聘-複合メガ災害PTSD・累積ストレス反応対応への精神分析の普及のために- | |
| 日本思春期青年期精神医学会 | 松田 文雄 | 市民公開講座「思春期今昔」 | |
| 助成先 | テーマ | ||
|---|---|---|---|
| 所属またはグループ名 | 代表者名 | ||
| 放送大学大学院修士課程生活健康プログラム | 伊藤 佳七子 | 歯科衛生士学生の実習期間中における心理社会的ストレッサーの実態とメンタルヘルスへの影響とメカニズム | |
| 慶応義塾大学高齢者研究グループ | 木元 麻鈴 | 後期高齢者の「孫とのかかわり合い」をめぐる心情について | |
| 就実大学 | 林 秀樹 | G.Musicによる精神力動的心理療法の課題と日本への導入可能性 | |
| 国立精神神経医療研究センター認知行動療法センターCT-R研修チーム | 三田村 康衣 | 精神科医療に携わる医療従事者のバーンアウトリスク軽減~パーソナルリカバリーに焦点をあてた研修からの検討~ | |
| 帝京大学文学部心理学科 | 尹 成秀 | 背面椅子式設定における被面接者の情緒的体験-生理指標の測定および質問紙による検討- | |
| 福岡大学医学部精神医学教室 | 原田 康平 | ポスト・ビオニアン的観点から見た「もの想い」概念の展望 | |
| 南青山心理相談室 | 森 一也 | 現代の多様性に応じた力動的アプローチの初期訓練に関する検討 | |
| 保育精神分析臨床研究会 | 田村 和子 | 保育関係者が対応に苦慮する保護者と保育士の特徴 | |
| 防衛大学校総合教育学群外国語教育室 | 尾崎 貴久子 | 中世イスラム医学における「メランコリア」の治療:食養生法を中心に | |
| 一般社団法人SST普及協会 | 加瀬 昭彦 | SSTで温かい社会を創る国際学術交流2025 | |
| 国際力動的心理療法学会 第29回年次大会 | 中村 有希 | 国際力動的心理療法学会 第29回年次大会:成熟に向けての力動的心理療法への外国人研究者の招聘 | |
| 福島復興心理教育臨床センター | 橋本 和典 | 福島における復興燃え尽き症候群の心理療法手法の開発と評価-精神分析家Freudenbergerのバーンアウト概念再考- | |
| 福井県立大学 看護福祉学部看護学科 | 平井 宏美 | 産後の母親が養育に適応していく過程で発揮する精神的回復力(レジリエンス)に影響を及ぼす内的要因の解明 | |
| 日本精神分析協会 | 藤山 直樹 | こころの臨床家一般への精神分析の啓発活動のための費用 | |
| 慶応義塾大学医学部精神神経科 家族だけ療法研究会 | 宗 未来 | 重症・遷延性の成人神経症性やせ症患者に対する家族焦点型の家族療法(”家族だけ”療法)の傾向スコア分析を用いた効果検証研究 | |
| 医療法人慶神会武田病院 リワークプログラム研究チーム | 加来 明希子 | 認知行動モデルに即した効果的な復職支援の検討 | |
| 日本思春期青年期精神医学会 | 松田 文雄 | 市民公開講座「思春期臨床から見る子どもの現実(リアル)~発達支援の現場から」 | |